 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし 日本の七十二候 霞始靆(かすみはじめてたなびく)
寄稿者:橋本繁美雨水 次候遠くの山々に薄ぼんやりと春霞がたなびき、ほのかに見える風景に趣が加わるころ。いかにも春らしいのどかさ。気象用語には「霞」はないが、同じ自然現象のものでも、春には霞といい、秋には霧と呼び分けている。さらに、昔の人は、...
 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし 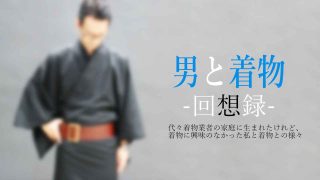 男と着物 - 回想録 -
男と着物 - 回想録 -  旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  京の旬感
京の旬感 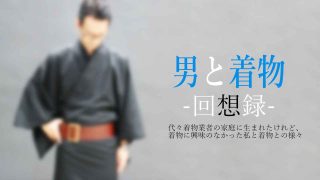 男と着物 - 回想録 -
男と着物 - 回想録 -  旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  寄稿記事-ことばの遊園地-
寄稿記事-ことばの遊園地- 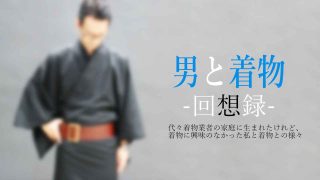 男と着物 - 回想録 -
男と着物 - 回想録 -  旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  京の旬感
京の旬感