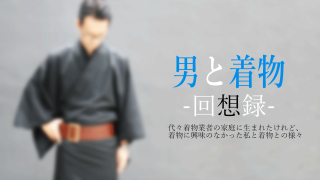 男と着物 - 回想録 -
男と着物 - 回想録 - 81 着物を掛けっぱなしにしたい私1
投稿者:ウエダテツヤ着たあとに干して畳んでタンスにしまう。着物にはよくある流れだ。私も着る頻度の少ないものはそういう流れになる。しかし日々着るものになると、面倒になってしまう。そもそも「干して」の段階で少し思案する。着物を吊り下げる場所が意...
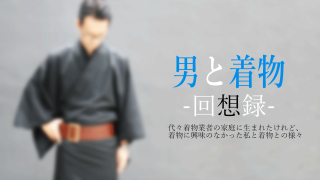 男と着物 - 回想録 -
男と着物 - 回想録 - 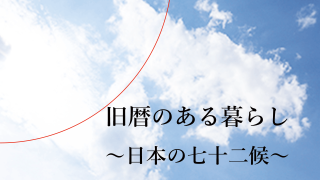 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  枡屋儀兵衛 商品
枡屋儀兵衛 商品  奄美探訪記と大島紬
奄美探訪記と大島紬 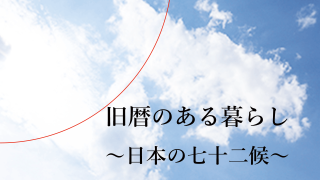 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし 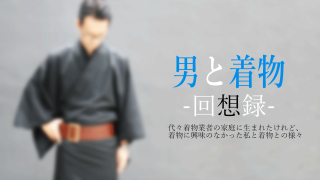 男と着物 - 回想録 -
男と着物 - 回想録 -  Kimono Factory nono
Kimono Factory nono 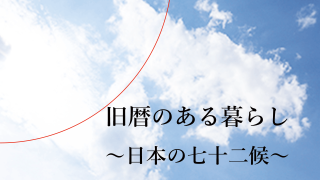 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  寄稿記事-ことばの遊園地-
寄稿記事-ことばの遊園地-  奄美探訪記と大島紬
奄美探訪記と大島紬