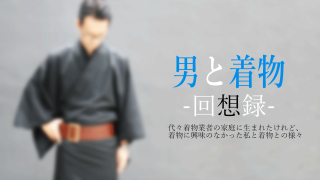 男と着物 - 回想録 -
男と着物 - 回想録 - 83 着物で自転車に乗る
投稿者:ウエダテツヤ学卒後に他府県へ出て7年後に京都に戻った。学卒までは実家に住んでいたけれど、一旦他府県に出て戻った時には実家から会社がバス通勤必須だったこともあって会社近くに住んでいた。近くと言えど徒歩で20分ほどだったので、毎日着物を...
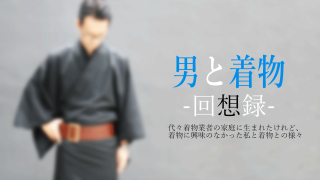 男と着物 - 回想録 -
男と着物 - 回想録 - 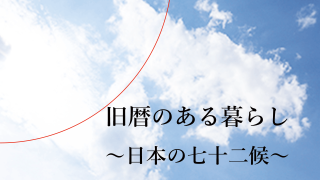 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  奄美探訪記と大島紬
奄美探訪記と大島紬 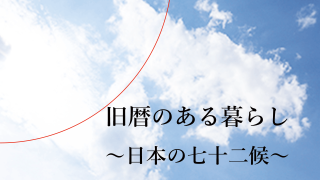 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし 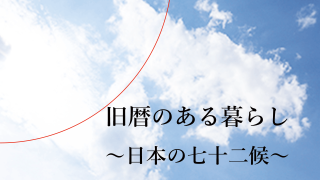 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  京の旬感
京の旬感 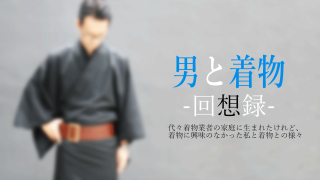 男と着物 - 回想録 -
男と着物 - 回想録 -  Kimono Factory nono
Kimono Factory nono 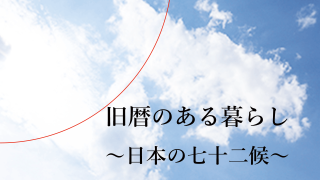 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  奄美探訪記と大島紬
奄美探訪記と大島紬