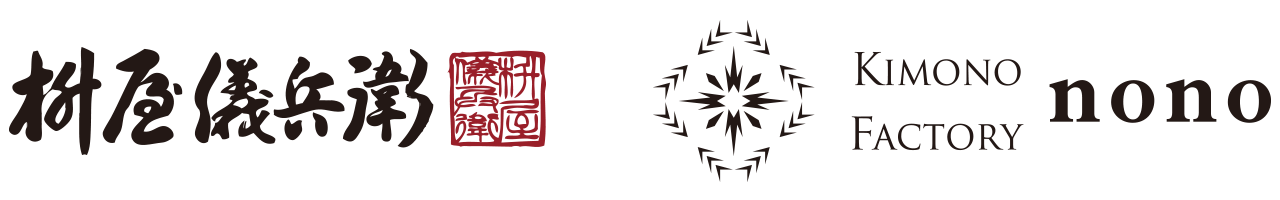寄稿者:橋本繁美
珊瑚の破片でできた白い砂浜と、エメラルドグリーンに染まる海の色。砂浜に群生するアダンの鋭い葉とパイナップルのように赤黄色く熟す大きな実。力強く広がるソテツの葉。生命力あふれるパパイヤ。白く優しいハマユウやユリの花。そこに訪れる蝶や鳥たち。群生するクワズイモやヒカゲヘゴといった亜熱帯のさまざまな植物群。手つかずの自然が残された奄美大島の魅力が、大迫力で語りかけてくる田中一村の世界。みる人を一気に虜にする人だ。
一村は、自然を偽って描くことを極端にきらったといわれる。一つの植物をモチーフに選ぶと、その植物を知り尽くすまで調べ、スケッチするのが常だった。一羽の鳥でもさまざまなポーズを研究して写生した。絵にふさわしいポーズのスケッチがなければ、鳥がそのポーズをとってくれるまで待ったという。自然の事物は、それぞれ必然性を持って存在しており、その必然性の中に生命を保っているだけに、嘘やごまかしが存在する余地などない。そのモチーフを十分に研究し、知り尽くしておけば、大胆なデフォルメもその生命力を失うことなく、むしろ生き生きと描くことができるのだろう。
手許に、奄美群島日本復帰50周年記念として開かれた『奄美を描いた 田中一村展』の図録がある。最終ページのクレジットには、平成16年(2004)1月2日発行、編集・制作は日本放送出版協会(プロジェクト21)、発行元は奄美群島日本復帰50周年記念『奄美を描いた 田中一村展』実行委員会、印刷は日本写真印刷株式会社と記されている。そこから一部抜粋させてもらおう。
昭和33年(1958)12月、奄美大島に降り立った一村は名瀬市屋仁川の梅乃屋に下宿した。翌年秋、そこを出て有屋集落にあるハンセン病院和光園の官舎に移り住む。この頃、親しくつき合ったのが、和光園の小笠原登医師と、事務長(当時は庶務課長)の松原若安氏、そして本願寺の福田住職、レントゲン技師で詩人でもありカメラに詳しい中村民郎氏等であった。
漢方医だった小笠原医師の話す薬草学のうんちくを極めた話は、本当に面白かったようだ。カメラについての中村氏との会話。そして福田住職のいけばなの話。それは、日本画の構図につながる、一村にとっては、興味尽きない世界のようだ。
孤高のうちに過ごしたといわれている奄美での生活も、初期の頃はこういった人生の達人、博学の友人たちに囲まれた、奄美理解を深める至福の時だったのかもしれない。(略)
また『日本のゴーギャン 田中一村伝』南日本新聞社編(小学館文庫)には、次のような文章で紹介されている。
千葉での生活を清算し、絵筆一本の放浪の旅に出た。奄美で亜熱帯の自然に出合い、ここで終生の絵を描くことに思いを定めた。日本画にあまり描かれたことのない奄美の生命力あふれる自然は、一村の絵筆を奮い立たせた。奄美生活19年。生活苦と闘いながらの画業だった。昭和52年の秋の夜、借家で独り夕食の準備をしながら倒れ69歳の生涯を閉じた。生涯独身。志操高き画家のあまりにも不運な障害だった
明治41年7月に、栃木県下都賀に生まれ、幼い頃から画才を現し、米邨(べいそん)と号して南画をよくした。大正15年、東京美術学校に入学、日本画を先行した。同期には、東山魁夷、橋本明治、加藤栄三、山田申吾らがいた。のちに日本画壇で「花の6年組」(昭和6年卒)といわれたほど英才が集まった年である。その中でも異才といわれた一村であった。入学時には、「すでに南画の妙域に達せり」と教授連を驚かすほどの技量を修めていたといわれる。(略)しかし、東京美校は、わずか3か月で結核に倒れ、中退をせざるを得なかった。彫刻家であった父稲村の病気も重なり、一家を背負いながら、独学で画境開拓に励む逆境に立った。(略) 戦後の昭和22年、第19青龍展に『白い花』を初出品して、入選した。しかし翌年には、川端龍子と意見を異にし、以後画壇との接触をほとんど断ってしまった。若くして天才画家といわれ、並々ならぬ自負を持ちながら、志を得ず、野にあって苦闘を重ねた一村。奄美での19年間は、その「絵かき」人生をかけた日々であった。晩年まで絵筆に執念を燃やし続けた一村の胸に去来するのは、やはり東京美校の同期生たちの姿ではなかったろうか。(略)
一村の画業と生涯を語るには、まだまだ不足だが、作品を通して奄美の魅力をいっぱい教えてくれる。奄美では絵を売らず、紬染色工で生計を立て、奄美の自然を描き続けた一村。奄美に生き、奄美を描き、奄美で逝った画家。こんな男、めったにいない。田中一村さん、また会いに行きます。