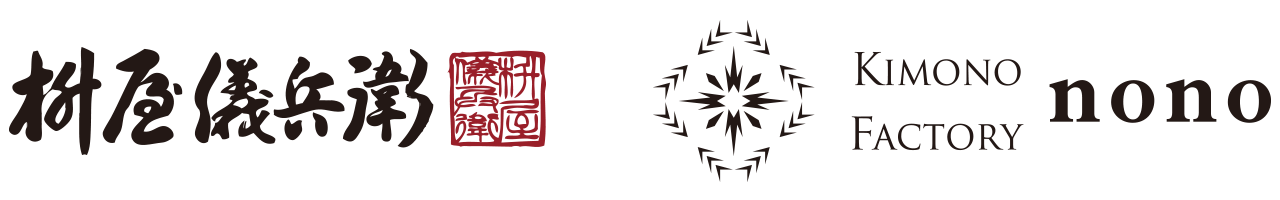寄稿者:橋本繁美
海。奄美の島をぐるりと縁どるサンゴ礁。海のなかでも最も生き物たちであふれた場所だ。いにしえから奄美には、暖かい黒潮の流れに乗って、さまざまな生物が寄り合い、人々に大きな恵みを与えてきた。奄美の人々はこの恩恵に感謝し、海のかなたにネリヤカナヤという豊穣をもたらす永遠の神の国があると信じた。森の水は海の生命たちを育て、また天に還り、森に降る一滴の雨水となる。生命は生まれ、めぐっていく
「生命めぐる島・奄美 森と海と人と」ホライゾン編集室編・南日本新聞社刊より
写真家・浜田太さんの本が手もとにある。ずいぶん前に、奄美空港で手にした情報誌「HoRiZon(ホライゾン)」の表紙に目が釘付けになったことを覚えている。そのときに知った写真家だ。写真展にもよせてもらった。奄美から京都に戻ってからは、いきいきとした奄美の魅力を教えてくれる写真集のなかで散策していたように思う。何ひとつ知らなかった奄美の自然、海を潜ることでサンゴ礁や魚たちを目にすることができ、偉大なるグランブルーの世界をほんの少しずつ知ることができた。
その歓びを写したいとカメラを持ち込み、挑戦するほどダイビングに余裕ができたのか、水中撮影をはじめた。一眼レフで鍛えた腕を海のなかで生かしたいと思っていた。しかし、手持ちのカメラを専用機材にするには相当な費用がかかるため、当時、出はじめた手頃なデジタルカメラを、水中用の専用ケースに入れて一緒にダイビング。ところが、いまでは考えられないくらい画素数も粗く、水中でのシャッター速度の遅いこと。ましてや、フラッシュを使おうとすれば、さらにシャッターチャンスを逃すばかり。目の前に魚が現われ、ここぞとシャッターを切ったところ、撮った画像には魚の姿なしのハズレが多かったこと。でも、海のなかで素人ながら、仲間たちとの記念写真に役立った。面白かった。最近のカメラなら、もっといい写真が撮れると思うのはよくないか。機会があればまた撮りたいものだ。
一般的にビギナーは、1本の酸素タンクで50分、60分ほど潜ることができるといわれる。もちろん、ベテランほど酸素の使い方が上手く、長い間潜ることができる。ところが、なぜか私は息づかいが粗く、タンクの持ちが40分少々と短かった。そう酸素の消費量がみごとにはやい。本人はできるだけタンクの酸素を上手に使おうと心掛けるのだが、手もとのエアーメーターはどんどん減っていく。それだけに、人よりははやく、ボートに上がることになっていた。
そんなある日のこと。ボートの上で、みんなの帰りを待っていたら、突然、疲れ切った女性がボートに近づいてきた。自分のチカラだけでは、船上に戻れないため、こちらも必死で引き寄せ持ち上げて、なんとか船上に。重たい機材を外し、とにかく横にして誰かの帰りを待っていたら、先生やインストラクター、生徒たちも次々と戻ってきてくれた。応急処置を受けて戻るしかない。だが、海の上では電波状況が悪く、携帯電話は繋がらない。船の無線機で港と連絡をとり、救急車の手配で無事病院へ搬送となった。なんとこの女性は朝、船上で知った京都山科からきた医療関係の女性陣の一人だった。原因は体調不良。自分の体調管理ができていないのに潜りは絶対禁物。無理や無茶は命取り。みんなにも迷惑がかかる。自然は怖い。いくら奄美でも甘く見てはいけない(?)ま、人よりはやく上がっていた誰かさん、人命救助とは大層だが役に立つこともあったという話。当時、京都に戻った私は、むろん得意先のヘルスメーカーで血圧計を2台購入して、ダイビングスクールに送ったのを覚えている。何事も、常に体調管理が基本なんだ。(つづく)