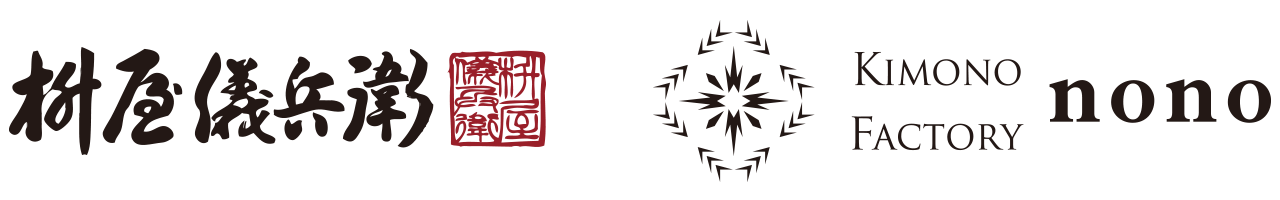寄稿者:橋本繁美
春を連れてくる雨。これは行友李風 (ゆきともりふう) 作の新国劇『月形半平太 (つきがたはんぺいた) 』の京都・三条河原町で、主人公が傘を差し掛ける舞妓にいう有名な一節。小雨の中を傘なしで歩くときに、気どった言葉として使う。いまどき、そんな人はいないか。春雨とは、霧のようなこぬか雨だけに、傘をさしても埒があかないことから、この名台詞が生まれたといわれる。なんと昔の人は、そぼ降る春雨をたのしむといった、流暢な感覚を身につけていたのは確か。この時期、ひと雨ごとに春めいてくるが、三寒四温の頃だけ、半平太のように春雨に打たれる風情はほどほどに。
【月形半平太】
行友李風の戯曲。4幕。大正8年(1919)沢田正二郎らの新国劇により初演。幕末の京都を背景にした、長州藩士月形半平太を取り巻く恋と剣の物語で、劇中の「春雨じゃ濡れて行こう」の台詞が有名。モデルは武市瑞山 (たけちずいざん) (通称、半平太)とされる。
【あらすじ】
京都円山で雨宿りをしていた祇園の芸妓染八は、折から来合わせた長州藩の志士月形半平太の立派な姿に心を惹かれた。半平太はその後、三條河原で桂小五郎と薩長土三藩連合による倒幕を策し、その帰り路の橋上で、会津藩の早瀬辰馬という青年武士と知り合い、お互いに好感を持った。数日後、見回組の先頭に立って半平太の下宿を襲った辰馬は、そこではじめて先日の橋上の人物が何者かを知った。半平太はその場をのがれ、彼の身を案じている芸妓梅松や舞妓の雛菊の許へ姿を見せたが、そこにも目明かしの眼が光り、自身の身辺の追求が激しくなったことを知った。辰馬は隊長奥平が、舞妓の雛菊に半平太の居処を白状させようとせめ立てる様子を見て、彼女をかばったことから、奥平と対立、危く討たれようとしたとき半平太が現れて、かえって奥平を切って捨てた。奥平に世話になっていた染八は、旦那の仇討ちをするため半平太を陥れようとするのだが、最後にはその男らしい姿に思わずこれをかばって短刀で肩をさされてしまった。そして半平太の手厚い看病を受け、時代の正義に生きる彼を愛するようになった。梅松はそうした染八を嫉妬したが、彼に寝がえりを打った長州藩士と新撰組の術策とも知らず大乗院へ乗り込む半平太に、梅松を秘かに会わせてやったのは染八であった。雛菊のとどけた西郷の手紙で半平太の危険を知った辰馬をはじめ、はじめて半平太の正しさを悟った長州藩士たちが駆けつけたときは、しかし、すでにおそく、急をきいて来た染八や梅松の幸福を祈りながら、いさぎよく散って行ったのだった。
(キネマ旬報データベースより)

春眠暁を覚えず
唐の詩人、孟浩然(もうこうねん)の「春眠暁を覚えず、処処啼鳥を聴く、夜来風雨の声、花落つること知んぬ多少ぞ」。うつらうつら夢でも見ていたときの詩なのか。春はなぜかやたらに眠くなる。寝る子は育つというが、そんな歳でもない。最近では短時間の昼寝をとって、午後からのエネルギーに備えるというのがビジネス街でも流行っているらしい。あくまでも短時間。ここで寝すぎると、余計に疲れるらしい。睡眠は時間でなく、眠りの深さ。なにかと精神疲労が続く現在。身も心もリラックスして、人間のからだの働きにあった固有のリズムで睡眠がとれると聞く。緊張と不安にさいなまれたりするときは、なかなか寝つかれなくなるので、ちょっとした運動で気分を発散したり、お風呂に入って首や肩のこりをほぐしたりする。ほんの少しの寝酒も快眠への道とか。アルコールはあくまでも適量、厳守。
花に色があるのは
美しいから。鮮やかだから。そこに惹きつける魅力、要素があるから。私たち人間の視覚を通せば、そうだろう。花にはなぜ色があるのか。それは、自然界において目立ちたいからだといわれる。というのは、花粉の媒介を風によっている風媒花は、たとえば稲の花のように、ほとんど目立たないが、鳥媒花や虫媒花は、豊かな色で鳥や虫にその存在をアピールしているからといわれる。これは花の匂いについてもいえることらしい。ただし、鳥や虫が感じる光の波長は人間の感じ方とは違っており、ミツバチは人間が色として感じていない紫外線を敏感に感じとっていることが、実験によって確かめられている。花の色や形の美しさは、「神のみわざ」を見るか、あるいは生存に都合のよい性質をもつ種類が、その性質を強めつつ生き延びてきた進化と見るかは、人生観の相違とか。なるほどね、そろそろ桜の花だよりが聞こえてきそう。(参考文献:倉嶋厚著『風の色・四季の色』)