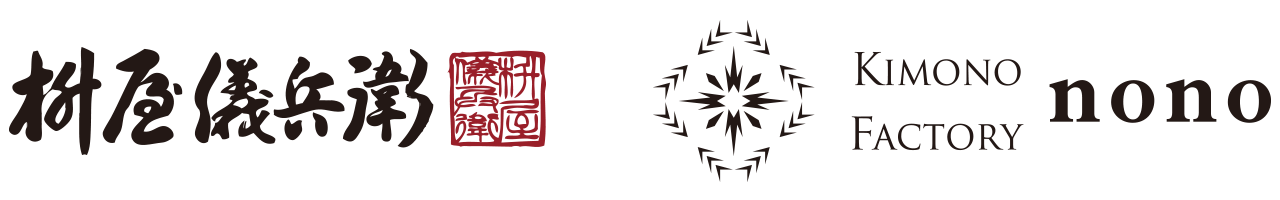投稿者:ウエダテツヤ
毎日のように着物を着て何年か経つと、徐々にそれは私にとっての普通になった。もちろん良い意味で習慣、日常のライフスタイルとして獲得したのかもしれないけれど、それよりも「刺激が感じられない」という良くない意味合いが大きかった。人の視線が気になっていた頃などどこへやら、街に着物姿が増えたことも相まって、良くも悪くも視線を意識出来なかった。
もともと着物大好き、着物を着たいというところから入らなかった私だったけれど、ムキになって毎日着てみると、人に興味を持ってもらったり新しい知り合いができたりして楽しかった。しかしそれは着物を着ることで着物から与えてもらったものであって、受動的。ある程度一巡しその受動的な刺激を使い果たすと「着物の魅力に頼っているけれど結局のところ私にとっての着物はどうなんだ」と着物に問われるような気がしてきた。ムキになるだけでは解決できないものがそこに横たわっていた。
刺激の感じられない日々。着る動機に義務感が色濃く反映され、けれどどうすることも出来なかった。そんな自分が好きになれず若い頃に覚えた停滞への燻りのようにジリジリと何かが損なわれる気がしていた。
それでも気付かない私は「着ればいいのだ」と思っていた。もはや「ただそこにあるものを手にとって着る」そんな感覚だったにもかかわらず。それは街で見かける着物姿の動機とは全く異なるものになっていた。
そうして着物に愛想をつかされたように、その関係は握った砂のようにスルスルと流れて落ちていた。何となく分かっていたけれど、理解できずにそれを眺め、そして変わらず握り締めるように着物を着続けた。物足りなさと対峙せずとにかくその手の中に押し込んでいた。着物を着ない理由や着たくない気持ちを聞くと悔しさとともに言い様のない苦味が込み上げたのは、それを自分自身で解決できていなかったからだと思う。「それでも私は着ているのに。」そんな風に思っていた。着ることによって得られる上辺は剥がれつつあった。(つづく)