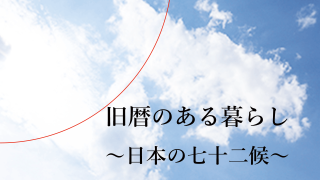 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし 日本の七十二候 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)
寄稿者:橋本繁美大暑 初候もっとも暑い期間とされる大暑のこの時期、花が終わると卵形の固い実がなるころをさす。一般でいう桐は4~5月の初めごろに、枝先に釣鐘型の薄紫色の花を咲かせる。古来、桐と青桐はよく混同されてきた。どちらも大きな葉を茂らせ...
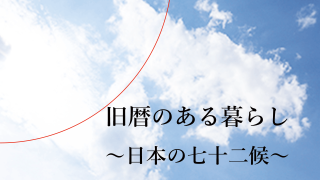 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  寄稿記事-ことばの遊園地-
寄稿記事-ことばの遊園地- 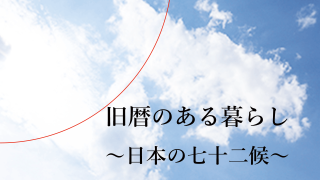 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし 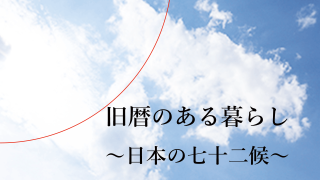 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  奄美探訪記と大島紬
奄美探訪記と大島紬 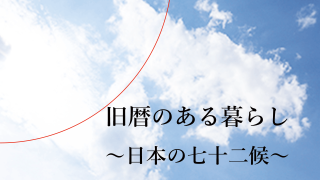 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  奄美探訪記と大島紬
奄美探訪記と大島紬 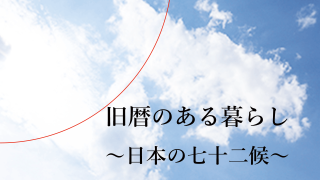 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし  奄美探訪記と大島紬
奄美探訪記と大島紬 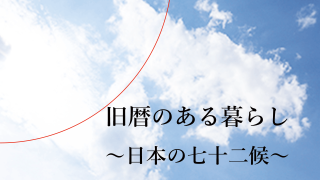 旧暦のある暮らし
旧暦のある暮らし