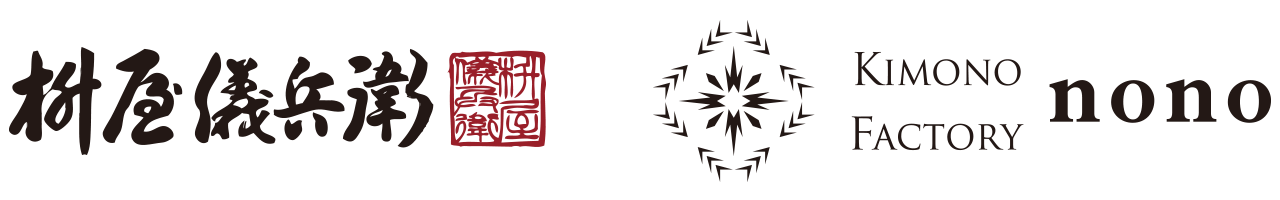寄稿者:橋本繁美

前回は奄美大島の金作原原生林を紹介したので、今回は京都の愛宕山を紹介したい。というのは、今から十年ほど前までは、枡儀さんところの新年会は、愛宕山に登って、火伏せ・防火に霊験あらたかな愛宕神社にお詣りし、帰りは水尾の方面へ下りて、松尾さんのお家で柚子風呂に入り、鶏なべをいただくというのが定番だった。なんと神聖なる行事ではないかと思いつつ、私も参加させてもらっていた。
朝、JR花園駅で待ち合わせ、タクシーに分乗して鳴滝の登り口に向かう。軽く準備体操をして、いざ出発。山登りの基本はゆっくり。マイペースで歩く。若い社員たちは競うように急ぎ足で進んで行く。とにかく元気だ。寒かった身体が体温を取り戻し、少しずつ熱くなってくる。先は長い。歩いても、歩いても、風景はあまり変わらない。見晴らしはない。はやくも息があがってきたが、とにかく一歩ずつ前へ進めるしかない。途中、部活の男子数名が勢いよく駆け上っていく。若い、パワフルだ。ただひたすらに歩くというのは、まるで哲学のように自問している自分がいる。独りになって、いろんなことを考える。反省ばかりか、情けない。そしてようやく愛宕神社の入り口の石段に。ここまでくると雪化粧。登山靴に滑り止めをはめ、最後のチカラを振り絞ってゴール。ストーブにあたると、身体全体から湯気が出ているのがわかる。神社にお詣りし、御札「火迺要慎(ひのようじん)」を授かり下山。

水尾の方に下りて、松尾さんのお家へ。まわりは柚子畑が多い。このあたりは松尾さんの姓が多いと聞く。毎年お世話になっているところなので、帰省した実家のようにやさしく迎えてくださる。すべて上田真三さまのおかげだ。まずは柚子風呂に入って、身体の疲れを癒す。そして、お待ちかねの新年会。当時、会長だった上田さんのご両親をはじめ、山登りに自信のないスタッフも揃って宴のはじまり。京の木屋町にある鳥彌三(とりやさん)で水炊きの味を研究してきたというご自慢の鶏なべ。おいしい湯気が部屋中に広がり、みなさんいい顔になっていく。ご馳走をたらふくいただいた後は、JR保津峡駅まで車で送ってもらい、山陰線に乗って京都駅へ。有意義な一日を終えた満足感、明日への兆しが見えたような気がした。また行きたいな。 ところで、みなさんは落語『愛宕山』はご存知だろうか。ここで一席、おまけ。
落語『愛宕山』
旦那のお供で、京の愛宕山へ山遊びにいった幇間(たいこ)の一八(いっぱち)。つらい山歩きに閉口したが逃げるに逃げられず大苦戦。仲間の繁八(しげはち)に助けられ、ようやく途中まで登ってきた。しばしの休憩である。そこに土器投(かわらな)げの的があり、土器が茶店で売っていた。
旦那は器用に投げて的に当てるが、一八はまるで当たらない。「今日はこれで試してみようと思ってな」と旦那が取り出したのが小判三十枚。周囲の止めるのを聞かず、旦那は三十枚の小判を全部投げてしまう。その小判を谷底まで拾いにいこうと、一八は茶店で傘を借り、落下傘代わりに傘を広げ、飛び降りようというのである。ところが、足がすくんで飛ぶことができない。「シャレに背中を押してやれよ」と旦那にそそのかされた繁八が、一八の背中をドンと突いたからたまらない。
傘にしがみついた一八は、風に乗ってスーッと谷底へ。「あった、あった、小判があった。旦那、三十枚みんなありましたよ」と大喜びで報告する一八だが、「どうして上がるぅ?」といわれてハタと困った。「欲張りぃー、狼に食われて死んじまえ」などの罵声を浴びて、一八は大慌て。
絹物の羽織・着物・長襦袢を裂きはじめて、縄をこさえようとする。その縄の先に石を結び、長い竹の先に引っ掛けて手許に引き寄せる。竹が満月のようになる。足で地をひとつトンと蹴った。ツ、ツ、ツ、竹のしなりを利用してヒラリと戻ってきた一八に、旦那はただ目を見張るばかり。「偉い奴だなお前は。一八、生涯贔屓にしてやるよ。ところで、金は?」「しまった。忘れてきた」。
参考文献:『落語大百科1』 川戸貞吉著 冬青社刊より